「世界のエリートはみなヤギを飼っていた」田中真知×中田考によるウイズコロナ小説【第1回】
第1回 リュウがカーナビと言い争って高速道路の星をめざすこと
「バカとは、自分をヘビだと勘違いしたミミズ」「人間はみなダメです。(中略)ダメなのは、何も知らないことではなく、知るべきことを知らないことです。知るべきことを知らない者をバカと言います。知るべきことを知らない者はどんなに物知りでも高学歴でもバカであり、知るべきことさえ知っている者は誰でもたとえ他に何一つ知らなくとも賢者です。」―――イスラーム法学者で博覧強記の怪人・中田考氏を、作家の田中真知氏が徹底インタビューして編まれた極辛劇薬人生論『みんなちがって、みんなダメ』(KKベストセラーズ)は刊行後話題になりベストセラーになった。その後続編が期待され続け、ついにここに誕生する!しかもなんと、「田中真知×中田考によるウイズコロナ小説」としてなのだ!題して『世界のエリートはみなヤギを飼っていた』。これから始まる驚天動地の展開にぜひ目を離さないでほしい。では連載第1回をお楽しみください。
■第1回 リュウがカーナビと言い争って高速道路の星をめざすこと
その朝はいつもとちがった。
目が覚めたとき、今日はきっとなにかが起きる。
とんでもないことが自分の人生に起きるという妙な確信がリュウの胸をざわつかせた。
とくに、変わったことがあったわけではない。
いつもとちがった夢を見たわけでもないし――もともと夢はほとんど見ない――窓から見える風景もいつもと変わりなかった。
薄めた牛乳みたいなはっきりしない雲に覆われた空の下、マンションの前の狭い道には車が渋滞している。見慣れた光景だった。大通りの混雑を避けた車がカーナビの示す迂回路の指示にしたがって、この狭い道に殺到するせいだ。
カーナビはバカだ。そのバカなナビをみんなが使っている。そいつらはもっとバカだ。リュウは車のひしめく通りを見下ろしながら思った。
みんな自分がナビを使っていると思っている
でも、そうじゃない。
本当はみんながナビに使われているんだ。
ナビに使われる人生なんてまっぴらだ。
オレはナビなんか使わない。
昨夜はマンションの前で追突事故があった。リュウが、バイトから帰ってくると、バンパーのひしゃげた車が二台、歩道に乗り上げ、双方のドライバーが「そっちが悪い」「いやそっちだ」と罵り合っていた。
リュウは思った。どうせ、どちらもナビのいいなりにこの路地に迷い込んでぶつかったのだろう、自業自得だ。
「いちばん悪いのはおまえらのアタマだ」
通りすがりに、リュウは心の中でつぶやいた、つもりだった。
ところが、二人はそろって、ものすごい形相でリュウをにらんでいる。
「おい、いま、なんていった?」
ひとりがリュウに詰め寄ってきた。
ちょうどそのときパトカーがやってきて、リュウはマンションに逃げ込んだ。
リュウは頭に浮かんだことを、そのまま口にしてしまう癖がある。
小さいときからそうだった。
小学生のとき担任になった女の先生が初めて教室に入ってきたとき、つい「うわあ、デブ!」といった。
先生がつかつかと近づいてきて、もう一回いってごらんなさいというので、もういちど「デブ!」といった。
読み聞かせの授業のとき、あまりにつまらなかったので「つまらない、つまらない、つまらない」といったら教室の外に出された。
「嘘をついてはいけません」とか「正直であることが大切です」とか説教するくせに、本当のことをいうと怒られるのだ。
あるときリュウは親に「あんたは病気かもしれない」といわれて病院に連れて行かれた。診察室に入ると医者がみごとにハゲていたので、リュウは「ハゲだ!」といった。
医者は「これは病気ではなく親のしつけの問題です!」と言い放って、リュウは追い出された。
でも、リュウも内心、自分は病気でなのではないかと思っている。
リュウは黙読ができなかった。
声に出さないと本が読めない。
小さい頃、声を出して絵本を読んでいると、大人たちに、ほお、読むのが上手だねえとほめられた。でも、そのうちまわりの子どもは声を出さずに本を読むようになった。でも、リュウは相変わらず音読をつづけていた。すると、以前は感心していた大人たちが、うるさい、静かにしろというようになった。勝手なものだ、とリュウは思った。
いまは多少はましになった。それでも気がつくと目にとまった文字を読みあげていることがある。電車に乗るときには週刊誌の中吊り広告に目がとまらないよう気をつけていた。
でも、そんなしみったれた過去にも今日でおさらばだ。
今日から新しい日が始まる。
理由はわからないけれど、リュウにはそうなるにちがいない気がした。
人生は変るときには変わる。
理由などわからなくても、自分の意志とかかわりがなくても、変わるときには変わる。
そのとき空にひろがっていたはっきりしない雲がふいに切れた。
朝日が幾すじもの光の束となって斜めに差し、遠くに見える高速道路の高架のあたりを明るく浮かび上がらせた。
リュウはデイパックと車の鍵を手にして部屋を出た。
かけ足で階段を下りると、マンションの裏の駐車場で車に乗り込んだ。
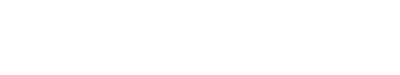


.jpg)









